平成14年11月2日〜7日にアメリカ合衆国オーランドで行われた第32回北米神経科学学会(Society for Neuroscience 32nd Annual Meeting)に参加した。昨年のサンディエゴでの学会は例のSeptember 11直後ということもあって、空港などはピリピリとした雰囲気に包まれていた。今年はその雰囲気も大分薄れているのだろうと予想していたが、実際に空港についてみると昨年にも増して徹底した荷物・ボディチェックが行われていた。逆に予想外だったのが参加者数で、昨年の23992人が21427人に激減していた(最終日朝の時点)。理由はよく分からないが、やや停滞気味のアメリカの景気と連動しているのだろうか?
 参加者数をみてもわかるとおりこの学会は巨大なものであり、会場には1500枚近くのポスターがずらりと並ぶ(写真1)。ただし、アメリカの会議場は流石にスケールが違う。会場のOrange County会議場では別の学会が同時開催されていたし、それでもまだスペースに余裕があった。さらに拡張工事が行われていたのだから、恐ろしい話である。
参加者数をみてもわかるとおりこの学会は巨大なものであり、会場には1500枚近くのポスターがずらりと並ぶ(写真1)。ただし、アメリカの会議場は流石にスケールが違う。会場のOrange County会議場では別の学会が同時開催されていたし、それでもまだスペースに余裕があった。さらに拡張工事が行われていたのだから、恐ろしい話である。
とにかく演題数が多いため、何でも見てやろうとすると食傷気味に陥ってしまう(それに、歩き疲れる)。今年は見て回る演題数をできるだけ抑えることに決めた。それでも一日あたり15件程度の演題は見ざるを得なかったのだが。中でも学会前から特に注目していたのがプリンストン大学のGrazianoのグループの研究である。彼らが、昨年この学会で示したのは、猿の大脳皮質運動野に比較的長い持続時間をもつ電気刺激を加えると、手の初期位置(腕の初期姿勢)によらず刺激部位に応じた一定の位置へのリーチング動作(手を所定の位置に到達させる運動)が生じるというものであった。体部位局在の概念(Penfieldの小人の図はおなじみであろう)からすれば、運動野のある部位への電気刺激は対応する筋を収縮させるだけのはずであり、リーチングのような複雑な動作が生じるはずがない。従来の概念では説明できない彼らのこの研究は大きな反響を呼んだ。
今回の彼らの研究3題はこの研究の続編であるが、そのうち一つは特に劇的な現象を取り扱っている。例えば、電気刺激によって最終的に肘を若干屈曲した姿勢が生じるものとしよう。肘を伸ばした状態では、運動野への電気刺激(0.2msecのパルス刺激、周波数200Hz、持続時間500msec)によって二頭筋が活動し、肘が屈曲することによってこの最終姿勢が達成される。ところが、肘を完全に屈曲した状態で与えた電気刺激は、三頭筋の活動を誘発し、肘を伸展させるのである。一次運動野の同じ部位を刺激しているのに、初期姿勢によって活動する筋が異なる?、この現象を一体どのように説明したらいいのだろうか。現時点でこの実験結果を説明する理論を我々は知らないが、リーチング動作を研究対象にしている研究者は非常に多いし、この結果をどのように咀嚼し従来の枠組みに取り込んでいくのか、今後の展開が楽しみになってきた。
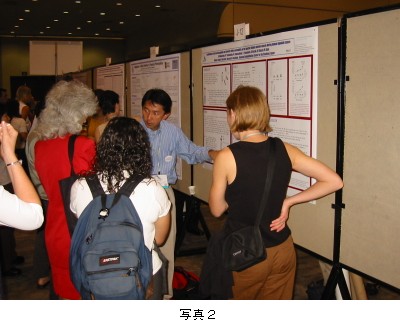 我々の研究室からは中澤公孝室長と私の二人がポスター発表をおこなった。中澤室長は、Facilitation of both corticospinal and stretch reflex excitability in the inactive tibialis anterior muscle during human bipedal stance(ヒト立位中にみられる前脛骨筋の皮質脊髄路および伸張反射経路興奮性の促通について)という演題名で発表した。彼の発表は非常に盛況で、午後1時から5時までの間、絶えることなく人だかりができていた(写真2)。
我々の研究室からは中澤公孝室長と私の二人がポスター発表をおこなった。中澤室長は、Facilitation of both corticospinal and stretch reflex excitability in the inactive tibialis anterior muscle during human bipedal stance(ヒト立位中にみられる前脛骨筋の皮質脊髄路および伸張反射経路興奮性の促通について)という演題名で発表した。彼の発表は非常に盛況で、午後1時から5時までの間、絶えることなく人だかりができていた(写真2)。
一方、私はAutonomous activity of human spinal motoneurons: Sustained muscle contractions with less involvement of motor cortex(ヒト脊髄運動ニューロンの自律的活動:大脳皮質運動野の関与の少ない持続的筋活動)という演題名で発表した。ヒトの脊髄運動ニューロンに独力で活動し続ける性質があることを示そうとした研究であり、個人的にはわりと自信もあったのだが、最終日ということもあって見に来てくれた人は20〜30名程度に留まった。それでも、この分野では著名なデンマークのHultborn博士が直々に見に来てくださり、意義深い議論を交わすことができたのは収穫だった。ただ、この研究は将来的に筋委縮予防法としての応用を狙っているので、臨床的な側面について議論する機会がもてればなお良かったかなとは思った。
私の発表が最終日であったことを除けば、十分満足のいく成果が得られた学会だったといえよう。それも、これだけの演題数がありながら、堕落せずに、どの発表も高いレベルを保っている研究者の良心・誇りの賜物ではないだろうか。そのおかげで優秀な研究者が集って、彼らから話を聞け、また話を聞いてもらえるのだ。来年も恥ずかしくない演題を用意したいものである。
 参加者数をみてもわかるとおりこの学会は巨大なものであり、会場には1500枚近くのポスターがずらりと並ぶ(写真1)。ただし、アメリカの会議場は流石にスケールが違う。会場のOrange County会議場では別の学会が同時開催されていたし、それでもまだスペースに余裕があった。さらに拡張工事が行われていたのだから、恐ろしい話である。
参加者数をみてもわかるとおりこの学会は巨大なものであり、会場には1500枚近くのポスターがずらりと並ぶ(写真1)。ただし、アメリカの会議場は流石にスケールが違う。会場のOrange County会議場では別の学会が同時開催されていたし、それでもまだスペースに余裕があった。さらに拡張工事が行われていたのだから、恐ろしい話である。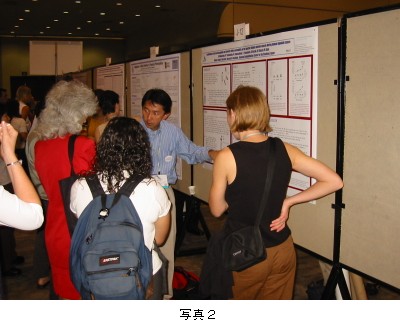 我々の研究室からは中澤公孝室長と私の二人がポスター発表をおこなった。中澤室長は、Facilitation of both corticospinal and stretch reflex excitability in the inactive tibialis anterior muscle during human bipedal stance(ヒト立位中にみられる前脛骨筋の皮質脊髄路および伸張反射経路興奮性の促通について)という演題名で発表した。彼の発表は非常に盛況で、午後1時から5時までの間、絶えることなく人だかりができていた(写真2)。
我々の研究室からは中澤公孝室長と私の二人がポスター発表をおこなった。中澤室長は、Facilitation of both corticospinal and stretch reflex excitability in the inactive tibialis anterior muscle during human bipedal stance(ヒト立位中にみられる前脛骨筋の皮質脊髄路および伸張反射経路興奮性の促通について)という演題名で発表した。彼の発表は非常に盛況で、午後1時から5時までの間、絶えることなく人だかりができていた(写真2)。